2023年4月、富山地方鉄道本線で発生した保線作業中の死亡事故が、2年を経て再び注目を集めています。
若干19歳の作業員が列車にはねられ命を落としたこの事故について、現場の責任者だった元社員の初公判が行われました。
裁判では、過失の有無と企業の安全管理体制が大きな争点となっています。
富山地鉄で起きた保線作業員死亡事故とは?
2023年4月、富山地方鉄道本線にて、保線作業中の19歳男性社員が走行中の列車に衝突され死亡するという悲劇が起きました。
事故は線路上での作業中に発生し、列車通過に際しての安全確認・待避措置が不十分だったことが原因と見られています。
事故当日は、複数回の列車通過が予定されており、2度の通過では適切に待避していたことが確認されています。
しかし、3度目の通過時に誤って線路内に残っていた作業員が列車と衝突する結果となりました。

初公判の内容と争点
2025年6月18日、富山地方検察庁により業務上過失致死の罪で起訴された元社員・堀内基被告(52)の初公判が開かれました。
検察側の主張
・列車通過前に作業員を退避させる義務を怠った。
・注意義務違反が直接的な過失であると主張。
被告と弁護側の主張
・被告は「その通りです」と一部認める。
・弁護人は「責任者業務に専念できていなかった」「内部規定に基づく教育が不足していた」と無罪を主張。
争点は、責任者である堀内被告が過失を負うべきか、それとも社内体制の不備が根本原因なのかという点にあります。

社内規定と安全管理体制の問題
富山地方鉄道の内部規定では、「現場作業と監督業務の兼務は禁止」と明記されています。
しかし、当時の現場では人手不足などを理由に、責任者である被告が自ら作業に従事する状況があったとされます。
さらに問題視されているのは、兼務禁止に関する社内教育が実施されていなかった点です。
このため、実務上の安全管理体制において現場でのルール遵守が困難だったとの指摘があります。
過去の対応と今回の違い
事故発生当日、列車は計3本通過しました。
最初の2回については、被告の指示により適切な待避がなされていました。
しかし、死亡事故が起きた3回目の通過では、作業員の1人が線路上に取り残されたまま列車が通過してしまいました。
この違いから、なぜ今回だけ適切な指示ができなかったのか、被告の対応の一貫性や業務負担との関連が焦点となっています。
今後の注目ポイント
今後の裁判で注目すべきポイントは下記の通りです。
・被告個人の過失がどこまで認定されるか
・富山地鉄の安全管理体制全体に対する社会的評価
・鉄道業界全体の労働環境見直しへの影響
この判決は、鉄道業界における作業安全の在り方を再考する重要な契機となるでしょう。
ネット上での反応と声
ネット上では、次のような意見が見られます。
・「若い命が失われたのは本当に悲しい」
・「責任者1人に負担をかける体制に問題がある」
・「鉄道会社は再発防止に本気で取り組むべき」
・「教育不足を言い訳にしてはならない」
・「鉄道会社の管理体制そのものが問われるべき」
・「再発防止の仕組みが社内にあるのか?」
世間の関心は高く、再発防止策に対する期待も大きくなっています。

まとめ
富山地方鉄道での保線作業中の死亡事故は、単なる現場の不注意では済まされない深刻な問題です。
責任者の過失の有無はもちろん、企業全体としての安全教育や管理体制が問われています。
判決の行方を見守りつつ、今後の鉄道業界における安全意識の向上が求められます。
当記事は以上となります。
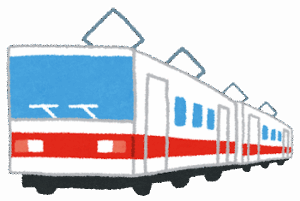

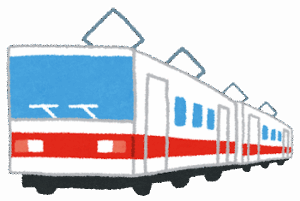



コメント