2025年7月18日、文化審議会は黒部市・宇奈月温泉にある「旧山彦橋」を国の登録有形文化財(建造物)として文部科学大臣に答申しました。
1924年(大正13年)に黒部川の峡谷をまたぎ、電源開発の拠点として建設されたこの橋は、トロッコ電車のビューポイントとしても親しまれてきました。
観光客や写真愛好家にも人気のこの場所が、ついに国の文化財として新たな注目を浴びています。
旧山彦橋とは?
建設時期と目的
大正13年(1924年)に、資材や作業員を輸送する専用軌道の橋梁として完成。
当時は「黒部橋」と呼ばれていましたが、後にトロッコ電車の音が山彦のように響き渡るとして「山彦橋」の名で愛されるようになりました。
構造と設計の特長
全長約93m、中央スパン約69mの鋼製スパンドレル・ブレーストアーチ橋。
橋脚を持たず一気に峡谷を渡る構造で、日本最古級の同形式橋梁とされています。
その後の沿革
1986年の宇奈月ダム建設に伴う線路付け替えにより鉄道橋としての役割を終え、遊歩道として再整備。
現在は市民や旅行者が自由に歩ける空間になっています。

観光スポットとしての魅力
アクセス抜群の撮影スポット
黒部峡谷鉄道宇奈月駅から徒歩約2分。
旧山彦橋からは新山彦橋と峡谷を背景に走るトロッコ電車を一望できます 。
遊歩道「やまびこ遊歩道」の紹介
旧軌道を活用した約1kmのコース。
鉄橋、トンネル、峡谷の絶景を楽しめる散策路で、無料で通行可(冬季閉鎖:11月末~4月下旬)。
四季折々の絶景
春の新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の雪景色…どの時期でも赤い橋と自然のコントラストが映えるフォトジェニックスポットとして人気。

文化財登録の意義と地域への影響
登録の経緯と県内の状況
国の文化審議会が7月8日に答申。
富山県内では80か所165件の登録有形文化財となり、橋梁としては3件目、黒部市では初の国登録です。
地域文化・観光への波及効果
富山県公式によれば、登録は“地域の宝”としての誇りを醸成し、観光資源としても活用が期待されるとのこと。
特に黒部峡谷と宇奈月温泉の観光ポテンシャルがさらに高まりそうです。

ネット上での反応と声
ネット上では、下記のような声が寄せられてます。
・「電車の音が山彦となって響く」
・「青い空や緑の木々に映える赤い橋」
・「写真撮影にぴったり」
地元メディアや観光ファンからは喜びと期待の声が上がっています。

まとめ
旧山彦橋は、歴史ある技術構造の橋梁としての価値だけでなく、トロッコ電車と黒部峡谷が織りなす絶景フォトスポットとしても高い魅力を持っています。
今回の国登録有形文化財への登録は、黒部市初の快挙であり、地域活性化や観光振興に向けた大きな一歩となるでしょう。
訪問を計画する際は、季節や列車の時刻を確認し、最高の1枚を狙うのがお勧めです。
ふるさと納税も併せていかがでしょうか。

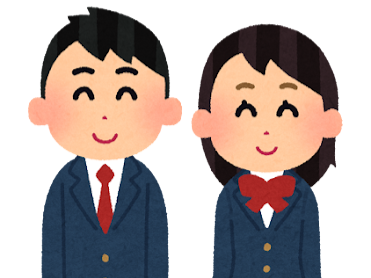







コメント