2025年夏、富山城址公園で相次いで発見されたサギの死骸。
その数はわずか1か月で107羽に上りました。
鳥インフルエンザなどの感染症は検出されず、原因はなんと人為的な「樹木伐採」のタイミングにありました。
当記事では、事の詳細や専門家の見解、富山市の対応などについて深掘りします。
事の経緯と原因
最初の異変が確認されたのは6月28日、公園の堀で2羽のサギが死んでいるのを巡回中の業者が発見。
その後、7月25日までに計107羽が死亡しました。
富山市の発表によると、原因はサギが繁殖・子育てをしている最中に、松の木6本を伐採したこと。
幼鳥の多くはまだ自立できず、巣を失ったことで餌を得られずに衰弱死したとみられています。
公園利用者からの騒音・糞害に対する苦情を受けての対応だったものの、配慮に欠けた結果となりました。
引用:チューリップテレビ
専門家の見解
富山県自然博物園ねいの里の間宮寿頼館長補佐によると、富山城址公園は高木が多く、外敵も少ないというサギにとって理想的な生息環境だったといいます。
今後については「公園内においてサギの巣作りを許容できる区域と、そうでない区域の明確な区分けが必要」と強調。
人間と野生動物が共存できる仕組みづくりの必要性が問われています。
富山市の対応と今後の対策
富山市は「野生生物への配慮を欠いた対応だった」と認め、深い反省を表明。
再発防止に向けて、下記のような対策を検討中です。
・サギの繁殖期を避けた環境整備の徹底
・公園内での生息可能区域の設定
・専門機関の意見を取り入れた意思決定と情報共有体制の強化
このような対策により、人間とサギが共存できる公園づくりを目指すとしています。
ネット上での反応と声
ネット上では、
・「行政の危機管理意識が低すぎる」
・「子育て中の伐採は非常識」
といった厳しい意見が多数見られました。
一方で、
・「苦情に対応しようとした結果」
・「両立は難しい問題」
といった声もあり、議論が分かれています。
いずれにせよ、「自然と共生する都市づくり」の在り方に改めて注目が集まっています。

まとめ
富山城址公園でのサギ大量死事件は、自然との関わり方を見直す契機となりました。
都市の中で生きる野生動物との共存には、計画的かつ科学的な対応が欠かせません。
今後、同様の事態を防ぐためにも、行政・市民・専門家が連携し、持続可能な都市環境の実現を目指すべきです。
当記事は以上となります。
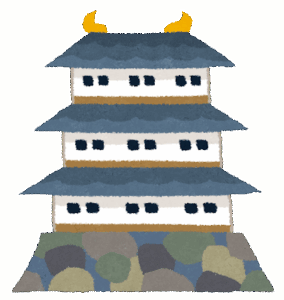










コメント